トップページへ| 文元社の本| 注文方法| 会社案内| 話題の本| 出版目録
|
現代教養文庫
『源氏物語入門』 −〔新版〕− 池田 亀鑑 著 |
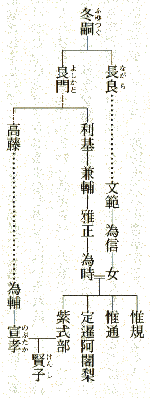
奥深い解説 五十四帖展望 千年を経た「物語」の中に現代を映す人間の姿がある。 雄大な、しかも美しい、人間曼陀羅としての長編小説「源氏物語」。 世界文学屈指の名作をよりたのしく読むためのガイド。 『源氏物語』は日本が誇る《世界の文学的遺産》 『源氏物語』が書かれたのは十一世紀、今から約一千年前。多くの人の批判に耐え、時代を超え国を越え、かくも長きにわたって愛読されてきた『源氏物語』の魅力と、作者紫式部の人物像および王朝時代の時代相について多面的かつ知的好奇心を刺激しつつ分かりやすく解説。 著者は生涯にわたりすべての精魂を源氏物語研究に傾注、その多くの学門的業績は“源氏学の泰斗"というにふさわしい存在。本書は、得がたい入門書となるだろう。 |
|
ISBN 4-390-11639-8 本体価格640円 256頁 2001年3月発行 現代教養文庫『源氏物語』(若い人への古典案内)秋山虔著はこちらへ |
|
|
書 名 源氏物語の本来の呼び方は、「源氏の物語」と「の」の字を入れて呼んだものでありましょう。同じ著者の作である『紫式部日記』にもやはり「の」を入れて呼んでおり、その他『更級(さらしな)日記』とか、前田家所蔵の『水鏡(みずかがみ)』にも同様にしるされております。「源氏の物語」とは、いうまでもなく、他の物語類の書名の例と同じように、物語の主人公である光源氏の略称からとられているものであります。もっとも源氏という字義をせんさくし、「源」は水の源てあって、「岷江初濫觴入楚乃無底」というように、この物語は、一見女がはかなく書いたもののようであるが、実は、その心は浅くないことをあらわすのだ、というようなことが、中世以後の註釈書には、よく言われました。中院通勝(なかのいんみちかつ)が書いた有名な註釈書である『岷江入楚(みんごうにっそ)』も、これを名としたものであります。しかし、もちろん、こういうことは儒学者流のこじつけでありましょう。 ところが、大原三千院に『拾珠抄(しゅうじゅしょう)』という本があって、それに安居院澄憲(あんごいんちょうけん)(一二〇三歿)という坊さんの書いた源氏供養の願文がおさめられております。いわゆる「源氏一品経(げんじいっぽんきょう)」ですが、その中に、これは「光源氏の物語」と呼ばれております。『河海抄(かかいしょう)』という古い註釈書には、源氏物語という名称の物語が世にたくさんあるので、他の源氏物語と区別するために、紫式部の作ったものを、とくに「光源氏の物語」と言ったのだというような、奇怪な一説をあげていますが、これはむろん信ずるにたりないことです。しかし、この一説はともあれ、「光源氏の物語」という名称が行われたことはたしかであります。たとえば、『東鑑(あずまかがみ)』の建長(けんちょう)六年(一二五四)十二月十八日の条にもその名称が見え、源氏学者である源光行(みなもとのみつゆき)の一派にも、そんな風に呼ばれていたようです。この名称も、さきの「源氏の物語」と同様に、主人公の光源氏によったものであることは、いうまでもありません。 そのほか、「紫の物語」、「紫のゆかりの物語」という呼び方がありました。それは、『更級(さらしな)日記』をはじめ、古い註釈書類にも見え、江戸時代の国学者である山岡浚明(やまおかまつあけ)という人などは、むしろこれをとりあげて、源氏物語は紫の上のことをもっぱら書いたものであるから、「紫の物語」と呼ぶ方が古く、後に「源氏の物語」と呼ばれるようになったのだと言っているくらいです。こういうことは、他の物語でもあることで、たとえば『竹取(たけとり)物語』は、「竹取の翁(おきな)の物語」と呼ばれるとともに「かぐや姫の物語」とも呼ばれました。これは要するに、その物語を主人公側から呼ぶか、女主人公側から呼ぶかのちがいに過ぎません。 ただし、ここで注意しなければならないことは、「光源氏の物語」にしろ、「紫の物語」にしろ、これらはすべて、作者みずからが命名し、決定した書名とは考えられません。もしも作者みずからが命名したものとするならば、このようにいくつもの書名が存在するはずはないでしょうし、また作者の命名以外に異名が生ずることもなかろうと思われます。これらの名称は、おそらく誰でもが容易に呼びうる一般の名称だったものと考えられます。このようなことは、源氏物語に限らず、平安時代の物語一般に共通した現象であります。 源氏物語のことを、「源語」、「紫文」、「紫史」などと呼ぶ例がありますが、これは明らかに漢文の形式にならったもので、江戸時代以後に行われたもののようです。 研究史及び研究書目 ……近代になってからも、源氏物語は日本文学研究の輝かしい座標をなしました。すぐれた歌人や作家は、だれでも源氏物語を愛読して人間教養の源泉としたのです。樋口一葉の文学を高くしたものは、元禄(げんろく)文学や「文学界」ばかりではありません。より以上に、源氏物語鑑賞できたえた、深くこまやかな情緒によるものでしょう。 なかでも与謝野晶子の業績は、多くの専門家たちに伍しても、めったにひけをとらぬものでした。源氏物語といえば、わずかに『湖月抄』ぐらいしか見られなかった時代に、一少女の身で全篇を読みとおしただけでも容易なわざではありません。しかも女史は、のちにみずからその現代語訳にあたりました。そして長い年月をかけてついに完成したのです。晶子は明星派(みょうじょうは)の中心をなした一代の大歌人であることにまちがいはないが、彼女のそうした旺盛な意欲、ロマンティックな熱情、それはみな、源氏物語研究への熱烈な愛情と、表裏一体をなしていたのです。 現代語訳といえば、晶子のほかにも、五十嵐力(いがらしちから)博士のもの、窪田(くぼた)空穂(うつぼ)氏のもの、それから谷崎潤一郎氏のものなどいろいろあります。舟橋聖一(ふなばしせいいち)氏もこれらとはちがった様式で現代化のためにつとめています。いずれも特色をそなえたすぐれたもので、誰でもができるというものではありません。たった一つの文章を訳すにしても、現代語のもつ一つの助詞、一つの助動詞のつかいかたで、ニュアンスがちがってくるのです。現代語訳は結局は訳者の創作的行為です。その人がいかに源氏を享受(きょうじゅ)したか、それを正直に語るものです。 大体このようにして、源氏物語は、一〇〇〇年という長い間、あらゆる階級、あらゆる種類の人々に読まれてきました。一口に読むといっても、その読み方には、実に多くの種類や階級のあることが分かります。そのなかにあるものは、真に源氏物語を正しく理解して、その本質にせまる努力をしているが、なかには源氏物語のために、何の貢献するところもない、むしろマイナスにしかならないものもあります。あるいはこの方が案外多いかもしれません。先にも述べましたが、仏教の宣伝のためにつかったり、好色本(こうしょくぼん)として珍重したりする、このようなことは、源氏物語をけがすものとして憤慨(ふんがい)されても仕方ありますまい。 しかし、よく考えてみれば、源氏物語は、果たしてそれくらいのことでけがされるものでしょうか。柳亭種彦(りゅうていたねひこ)が『田舎源氏』を書いて、源氏物語の世界をとんでもない方向にもっていったといっても、そのために源氏物語に、きずがついたというわけのものではありません。きずをうけたのは、『田舎源氏』の作者白身で、種彦という男の文芸鑑賞は、こんな卑俗な馬鹿げたものかと嘲笑(ちょうしょう)されるだけの話です。 その反対に、どんなすぐれた源氏学者があって、たとえば定家や親行などの人が、身をもって源氏物語の本質にぶつかり、生涯をその研究にかけたとしても、源氏物語の価値が、そのために特別あがったというわけにはなりません。価値があがったのは、そういう業績を残した定家や親行白身です。源氏物語は、一千年に近い時の経過の中に生きて、ほとんど無数といってよいほどの読者をもち、その一人一人によって、自由に気ままに扱われてきたわけですが、しかし源氏物語そのものは、依然としてただ一つ、あらゆる毀誉褒貶(きよほうへん) をこえ、すべての享受をこえて、毅然(きぜん)として天の一角にそびえている、不変の巨峰だといっていいのです。 このような偉大な作品にむかって、われわれがこいねがうことは、ただいかにしたら、おのれをむなしくして、この名作の不朽(ふきゅう)のいのちにふれることができるか、ということだけです。 最後に、なおこの物語について学ぼうとされる方たちの御参考までに、研究書目をあげることにします。もっとも源氏物語の研究書目は写本にしろ、刊本にしろ、余りにも多く、一つ一つあげることは到底不可能ですし、また、今は、その必要もないでしょうから、主要なもののみを適宜(てきぎ)にあげておくことにしましょう。…… 跋に代えて 『源氏物語』は日本文学の作品の中でも世界文学の上ですぐれた位置を占めてゆくことのできる少数の作品の一であります。平安時代の貴族生活を背景として、その中に多くの男性女性を生き生きと描いております。光源氏や薫君をはじめ男性の性格や心理をもすぐれて書きわけておりますが、殊に多くの女性の性格をあざやかに描いているのは驚くべきほどであります。『源氏物語』は紫式部が全部書いたのではないという説もありますが、他の人が一部分を書いたとしても式部以外にあれだけ描きうる作家として誰がありましょう。平安時代には『源氏物語』以外にも『宇津保物語』や『落窪物語』や『狭衣物語』、『堤中納言物語』その他ありますが、作品として『源氏物語』に及ぶものはありません。またあの流麗で繊細な韻律と情趣とをただよわせた文体はどの作品を見ても見い出すことができません。私には紫式部というすぐれた個性を思わずにはいられません。紫式部は人間としては清少納言ほどさっぱりした新鮮さはなかったかも知れませんが人間や生活を深く観照し、洗煉された文体をもってこれを形象化し得た点では世にも稀れな作家であったといわなければなりません。そうしてこの作品を多年にわたって描きつづけることによって式部みずからの人間形成を行ったと見られるのであります。 『源氏物語』を愛し、この物語の研究に大きな成果をあげた人々は古来多くあります。藤原定家や三条西実隆や本居宣長や萩原広道その他それぞれに立派な源氏物語研究を行っております。宣長の「もののあはれ」論の如きは長くそれ以後の源氏物語評価の規準になっております。近代になりましてからはそれ等先人の研究の跡をうけてその研究は一層精緻になって参りました。『源氏物語』を生涯の研究対象としてこれに学問的精魂を傾けている人々も多くなって参りました。中でも池田亀鑑氏は大学を卒業されて『源氏物語』の基礎的研究に志されてからは、すべての精魂を『源氏物語』の研究にささげておられました。そうしてその成果を発表してゆかれました。多くの協力者を得て完成されました『源氏物語大成』はその死の直前にいっさいの刊行を終わったのでありました。三十数年にわたる氏の苦行の成果で、源氏物語研究史の上でいつまでも残る業績であります。 こういう純学問的な仕事のほかに、氏は『源氏物語』の普及のためにも種々の仕事をされました。紫式部学会に於て『源氏物語』の講義をされたり、源氏物語劇の上演に舟橋聖一氏を助けて骨折られましたのもそれであります。『源氏物語入門』を世に出されましたのも『源氏物語』を広く一般に知らしめようとされたためでありましょう。これらの普及のための仕事にも、氏の多年の源氏物語研究の成果が織りこまれておりますから、十分信頼することができます。 氏が急逝されてからすでに半年を過ぎましたが、このたび『源氏物語入門』が装いを新たにして世に出ると聞いて氏のためにもまた源氏物語を愛好する人々のためにも喜ばしく存じます。この書を読む人が『源氏物語」をより愛するようになり、『源氏物語』の原作を直接に読む人が一人でも多くなるように望まれるのであります。それによって源氏物語の作品の価値がより広く認識されるとともに、『源氏物語』を通して人間がいかに生きゆくかという問題をお互に考えてゆくことができたらと存じます。 一九五七年七月 久松潜一 著者略歴 池田亀鑑(いけだきかん)博士は1986年(明治二十九)、鳥取県日野郡福成村で、小学校長の父池田宏文と母とらの間に長男として生れた。鳥取県師範学校を経て1922年(大正十一)東京高等師範学校を卒業し、女子学習院に奉職されたが、間もなく辞して、東京帝国大学文学部国文学科に入学、1926年(大正十五)卒業された。卒業論文の「宮廷女流日記考」は、実に一万八千枚におよぶ尨大な研究、成果であった。以後、芳賀矢一博士記念会の事業として委嘱された源氏物語注釈の編纂を中心として、平安朝文学研究に寸暇を惜んで日夜精進努力を傾注され続けた。1934年(昭和九)東大文学部助教授、ついで教授、大正大、慶大、早大、東洋大などの教壇にも立たれ、ながく学生の指導にあたられた。 平安朝文学研究においては斯界の第一人者であり、その学風は常に実証主義を重んじ、とくに困難をきわめる古典の本文研究に幾多の輝かしい業績をあげられた。主著には、1933年(昭和八)「伊勢物語に就きての研究」(二巻)、1942年(昭和十七)「校異源氏物語」(五巻)、1944年(昭和十九)「古典の批判的処置に関する研究」(三巻)、戦後多年を要した「日本古典全書・源氏物語」(七巻)、1956年(昭和三十一)完結し朝日文化賞に輝やく「源氏物語大成」(八巻)、および「全講枕草子」(二巻)などがあり、その赫々たる業績はながく学界に生き続けるに相違ない。 博士は1944年(昭和十九)ころより著しく健康を害され、1956年(昭和三十一)十二月十九日、哀しくも急逝された。享年六十。博士の深い学識と溢れるばかり純真な暖かい人柄を今なお追慕してやまぬ多くの人々によって、現在、郷里および多摩墓地の一角には文学碑が建てられ、故人を偲ぶよすがとなっている。 |
|
◆◆◆ |
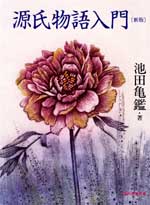 源氏物語入門 目次
源氏物語入門 目次